死亡にともなう年金事務所での遺族年金・未支給年金の請求について紹介します。
今回は特に厚生遺族年金について紹介します。

Contents
遺族厚生年金とは?
遺族厚生年金は被保険者が死亡した際に、その者によって生計を維持されていた遺族が受給することができる日本の公的年金の呼称です。
参考 遺族厚生年金加算額
「死亡した被保険者の報酬比例部分の年金額×3/4+加算」
支給条件
次のいずれかを満たした場合に支給されることになっています。
①厚生年金の被保険者が死亡した場合
②被保険者だった人が被保険者期間中の疾病がもとで、初診の日から5年以内に死亡した場合
③1級・2級の障害厚生年金を受給している人が死亡した場合
④老齢厚生年金の受給権者か受給資格期間を満たした人が死亡した場合
請求対象者
請求対象者は亡くなった被保険者に生計を維持されていた遺族です。
また次の両方を満たすことが支給条件です。
①死亡した人と死亡時に生計を共にしていること
②受給対象者となる遺族の年収が850万円未満
請求対象者には次の通り順位が決まっています。先順位の人が受給権を取得した場合は、後順位の人は受給権者の資格は与えられません。
①配偶者と子
②父母
③孫
④祖父母
年金額
死亡した被保険者の報酬比例部分の年金額×3/4(+中高齢寡婦加算)

請求できる期限
被保険者の死亡から5年以内
手続する場所
管轄の年金事務所
請求に必要な書類
遺族年金厚生年金裁定請求書
年金事務所の窓口に用意してありますのでその場で記入します。
亡くなった人の年金手帳や年金証書
戸籍謄本
亡くなった被保険者と請求者の関係がわかるものが必要になります。
死亡診断書のコピー
これは、死亡届を役所に提出したもののコピーです。
所得証明書
請求する人の所得額が確認できる証明書です。
住民票
これは、亡くなった被保険者と請求者との住所地が確認できるものです。
※亡くなった被保険者については、「住民票の除票」に記載されます。
ですので、請求者の「住民票」、被保険者の「住民票の除票」の各1通が必要になります。
受取人の印鑑
認印で大丈夫ですが、シャチハタ印はダメです。
振込先となる金融機関の通帳
振込先の金融機関口座の番号を記入するために持って行きます。
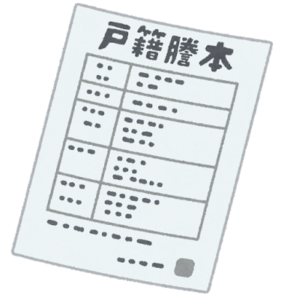
遺族厚生年金裁定請求書の記入について
記入方法については、年金事務所の相談員さんが丁寧に教えてくれるので心配はいりません。私も、相談員さんの指示に従って請求をしました。
年金事務所について
年金事務所へ出向く前には予約を入れた方がいいでしょう。突然、訪問するとかなり待つ場合も考えられます。
参考:未支給年金の請求
亡くなられた方の年金の支給は市役所に死亡届が提出されると、自動的に停止されます。
ご存命だった期間の年金が未支給の場合は「未支給年金」の請求が必要になります。
未支給年金の手続きは年金事務所で必要になるので、遺族年金の請求と同時にやってしまいましょう。
※必要書類も遺族年金の請求の時に使用するものと重複するので、特別に用意する必要はありません。

まとめ
いかがでしょうか?
亡くなられた方によつて生計を維持されていた方が必ず必要な手続きになりますので是非参考にしてください。
また、不明なことがあったら年金ダイヤルで確認してから手続きしましょう。
「ねんきんダイヤル」:0570-05-1165(ナビダイヤル)
受付時間:月 曜 8:30~19:00
火~金曜 8:30~17:15
第2土曜 9:30~16:00